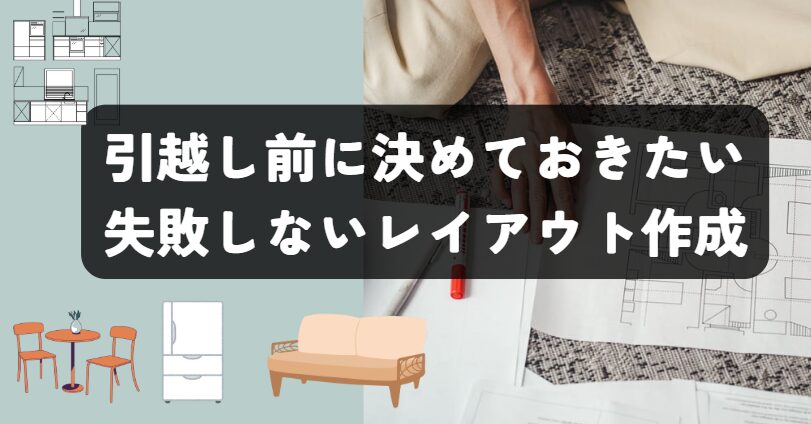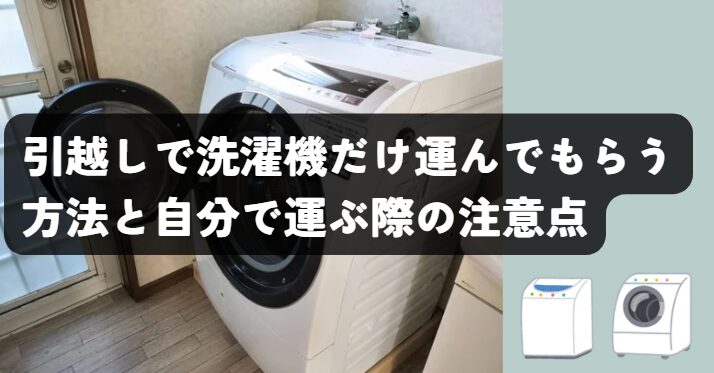引越しの荷造りを始めるタイミングって、意外と悩むポイントですよね。

できるだけ早く始めたほうが良いのはわかっていても、どう進めればスムーズに進むのか、コツや順番を知っておけば安心です。

今回は、引越しをスムーズに乗り切るための失敗しない荷造りの順番やコツ、最適なタイミングをお伝えします。
引越しの荷造りはいつから始めるべき?
引越しの荷造りはできるだけ早く始めたほうがいいけど、順番が大事です。
まずは、賃貸の場合、大家さんに連絡、新しい家を探し、引越し業者を決めることから始めます。
なぜならこの時期、引越し業者が決まって荷物をまとめるためのダンボールが届くことが多いです。
引越しでは、ダンボールを積んで運ぶので、丈夫で同じ大きさのものを揃えるのが大切です。

スーパーやホームセンターで無料でもらえることがありますが、汚れや匂いが気になることもあります。
少し手間をかけてダンボールを集めるより、ネットで引越しセット(ダンボール、ガムテープ、緩衝材)が買えるので、そちらを利用するのもおすすめです。
普段使わないものを先に梱包する
引越しの荷造りを始めるときは、まず普段使わないものや不用品が多く収納されている押入れを整理するのがポイントです。
不用品の処分には時間がかかるため、荷造りと並行して進めると効率的です。
ダンボール箱に入るものは整理してダンボールに詰め、布団などの大きなものは布団袋に入れて、荷造りが終わった状態で押入れに戻しておくと便利です。
この方法で部屋を広く使い、その後の梱包作業のスペースも確保できます。
玄関から遠い部屋の荷物を先にやる
引越しの荷造りをしている間も、普段通りの生活が続きますよね。廊下や玄関、リビングが荷物でいっぱいにならないようにしたいものです。

荷造りをしながらも快適に過ごすためには、玄関から遠い部屋から始めるのがいい方法です。荷造りを終えたダンボールは、その部屋に積み重ねていくことになります。
もし玄関近くの部屋から荷造りを始めると、部屋が狭くなって出入りがしづらくなってしまいます。
家族が多い場合は、「荷造りが終わった荷物はこの部屋にまとめよう」と決めておくのもおすすめです。
荷物の重さと箱の使い分け
引越し業者が用意するダンボール箱にはいくつかのサイズがあり、それぞれに適した荷物を入れることが大切です。
例えば、衣類用の大きなダンボールに、本やレコードなどの重いものをたくさん詰めてしまうと、引越し作業員でも持ち上げるのが難しくなったり、ダンボールの底が抜けてしまうことがあります。
基本的には、軽い物は大きな箱に、重い物は小さな箱に詰めるのがポイントです。これを守ることで、荷物を安全に運ぶことができます。
荷物ごとの荷造りのコツ
引越しの荷造りでは、輸送中に荷物が破損しないようにしっかりと梱包することが大切です。
引越し業者が荷造りや梱包を行った場合を除き、輸送後に荷物が壊れていた場合、外観に目立った損傷がなければ荷造りをした側が責任を負うことになります。
荷物にはそれぞれ適切な梱包方法があり、引越し作業中に荷造りの方法を改善するよう作業員から指示されることもあります。
ここでは、引越し作業員が行う荷物に合わせた箱詰めや梱包のコツをご紹介します。
食器類
食器類の梱包には、引越し業者が使うミラーマットという専用の緩衝材が理想ですが、なければ新聞紙でも十分に代用できます。
新聞紙を1枚広げて軽く揉みほぐし、空気を含ませてから使うのがコツです。
食器はひとつずつ丁寧に包み、重い食器を下に、軽い食器を上に置きます。お皿は平らに並べるのではなく、立てて並べると、上からの圧力がかかっても割れにくくなります。
箱をゆすってカチャカチャ音がする場合は、隙間に新聞紙を詰めて中身が動かないようにしましょう。
食器類の箱は重くなりやすいので、小さめの箱を使い、外側に「ワレモノ」や「食器」と書いておくと、誰でもわかりやすくなります。
衣類
コートやスーツなどの長い衣類は、業者が用意するハンガーボックスを使えば、ハンガーにかけたままシワをつけずに運べます。
しかし、ハンガーボックスを用意していない業者もあります。
業者によっては、洋服タンスの中身をそのまま運んでくれる場合もあれば、タンスの中身を出して箱詰めするように指示されることもあります。プラスチックの衣装ケースは中身が入ったままで問題ありません。
また、着物などの特殊な衣類には、専用のダンボールやケースを提供する業者も多いです。
一般的な衣類は、大きなダンボールにたたんで平らに詰めると上手に梱包できます。
本・レコード・CD
本やレコード、CD/DVDなどは、食器類と同じように引越し業者指定のダンボールか、小さめの箱に入れるようにしましょう。
箱の中で本やレコードが動かないように、隙間なく詰めるのがポイントです。特にレコードは立てて並べ、隙間ができた場合は新聞紙などの緩衝材を詰めて補填します。
箱を積み重ねる際には、本やレコードと箱の上蓋に隙間ができないように丁寧に梱包しましょう。
ダンボール箱が壊れないように、本やレコード、CD/DVDなどは詰めすぎないことが重要です。重さのバランスを考え、持ち上げられないくらい重いダンボール箱は避けるようにしましょう。
タンス・テーブル・ベッド
タンスやテーブル、ベッドの分解や組み立ては、ほとんどの引越し業者が行ってくれます。
ただし、分解や組み立てには、購入時に付属している専用の工具が必要な場合があります。これらの工具は引越し後もなくさないように保管しておくことが大切です。
さらに、現在の住居で吊り上げやクレーン作業を使って搬入した家具がある場合、そのことをあらかじめ引越し業者に伝えておく必要があります。
大きさや荷物の量によっては分解せずに運搬することもあります。
冷蔵庫
冷蔵庫や冷凍庫のコンセントを抜くと、庫内が外気温に戻る過程で結露が発生したり、冷凍庫の霜が溶けて水が出ることがあります。
引越しの前日か、遅くとも6時間前には冷蔵庫や冷凍庫を空にしてコンセントを抜きましょう。
この時、扉は開けたままにし、底に厚手のタオルなどを敷いて、結露や霜が溶けた水分を吸収させて庫内を乾燥させます。
引越しの一週間前ぐらいから、中身を少しずつ減らして、引越し当日には空の状態にしましょう。
洗濯機
多くの引越し業者は、洗濯機の取り付けや取り外しを標準サービスとして提供していますが、業者によっては有料オプションとしているところもあります。
洗濯機を運ぶ前には、衣類をすべて取り出し、水をきちんと抜いておくことが大切です。
また、ドラム式洗濯機の場合、輸送用の固定ねじ(輸送ボルト)がないと、輸送中に洗濯機が故障する可能性があるので、忘れずに取り付けておきましょう。
パソコン
パソコンを引越しする際、元の外箱と緩衝材があれば最適ですが、ほとんどの引越し業者は当日梱包をしてくれます。
テレビやオーディオと同じように、配線やインターネット接続の作業は有料オプションとして提供されていることが多いです。
さらに、引越し中にデータが損失した場合、引越し業者は責任を負わないため、大事なデータは必ずバックアップを取っておくことが重要です。
荷造りが終わらないが終わらない場合
多くの人は費用を抑えるために、自分で荷造りをするプランを選びます。
でも、もし引越し当日までに荷造りが終わらなかった場合、業者が有料で荷造りを手伝うことになったり、最悪の場合、引越しがキャンセルされることもあります。
荷主都合でキャンセルする場合、キャンセル料がかかります。当日キャンセルだと、業者は費用の50%を請求できることになっています。
オプションの荷造りサービスを利用する
荷造りに不安のある方や、仕事が忙しくて時間の取れない方は引越し業者の荷造りサービスを利用するといいでしょう。
料金は追加でかかってしまいますが、引越し当日までに荷造りが終わらないリスクを避けることができます。
荷物を減らす「断捨離」
使用頻度の低い荷物は思い切って処分しましょう。
私も何度か引越しましたが、その際は半分ぐらい荷物を処分していました。
私の場合は引越しの度に気持ちをリセットするつもりで「断捨離」を実行していましたが、人によってはなかなか処分できないという人も多いでしょう。
トランクルームなどに保管する
断捨離が難しい人向けにおススメなのが、一時的に保管できるトランクルームなどに荷物を非難させておく方法です。
これなら必要か不要かの判断を先延ばしにできます。
ただし、保管してる期間はお金がかかるので、あくまでも一時的な手段です。
まとめ
今回は、引越しをスムーズに乗り切るための失敗しない荷造りのコツや、最適なタイミングを紹介しました。
できるだけ、ダンボールに入るものは徹底的に箱詰めしましょう。
箱詰めすることでダンボールを重ねやすくなり、荷造りのスペースも効率よく確保できます。その結果、引越し当日の作業がスムーズに進み、荷物が破損するリスクも減少します。
さらに、きちんと荷造りされた荷物は、引越し作業員も丁寧に扱ってくれるので、安心して任せられます。
■関連記事
⇒働きながら引っ越し!ストレスフリーに引越しを成功させる秘訣
⇒引っ越し見積もりはいつから始める?失敗しないタイミングとポイント
⇒引っ越し見積もり高すぎ!?ぼったくり業者を避ける方法
⇒⇒引越し見積サイトがヤバイ?失敗しないための5つの注意点
⇒即日!引っ越し後すぐにインターネットが使える2つの方法